神社と社家の歴史
御宮と神主の物語
はじめに ― 表記について

例えば「すわ」→「須波」「諏訪」「諏方」のように、語られる時代や場面また記録者によって、様々な表記が見られます。社名は「諏訪明神」「諏訪大明神」「西諏訪大明神」「諏訪社」「諏訪神社」「諏訪宮」「秋田諏訪宮」等、祀職についても「祝子」「はふり子」「神主」「社掌」「社司」「宮司」等の記録が残されていますが、煩雑さを避けるため基本的に「諏訪宮」「宮司」の呼称を使用しています。本ウェブサイトの他の部分でも同様です。
「御宮と神主の物語」 少し長めですが、おつきあい下さい。
創建 拂田柵
払田柵 外柵南門(復元)
秋田諏訪宮は延暦21年(802年)、信濃國の諏訪大神を奉じて征夷中の征夷大将軍坂上田村麻呂により「拂田柵(ほったのさく)」の南方に柵と同時期に創建された、と伝えられます。秋田県内の多くの神社が田村麻呂将軍による創建を伝えていますが、田村麻呂自身は秋田県内に足を踏み入れていない、というのが定説となっています。これについては、陸奥・出羽両國間で経営の拠点となる城柵造営政策を同時に実施したもので、陸奥國では将軍田村麻呂が胆沢城と志波城を、これと並行して出羽國では副将軍文室綿麻呂が「拂田柵」を造営したと考えられ、後世には陸奥・出羽両國の全ての事績が偉大なる田村麻呂将軍のものと伝わったと思われます。ただし、田村麻呂の「巡見」のような事はあったのではないかとの主張もあります。
創建時の神社の場所は柵の近くであったろうと思われますが、のちに金沢に遷ったとされます。
後三年の役と諏訪大祝

源義家の求めに応じて後三年の合戦に参陣した諏訪大祝為仲は、当時は金沢に鎮座していた諏訪宮で祭祀を行ないました。菅江真澄は、金沢寺田村の茨嶋より七、八町入った山に諏訪明神の旧社地がある、と記録しています。寛治元年(1087年)凱旋に際して本殿に大祝像を祀らせ、当地に一男子を遺して諏訪宮の祀職と定めました。以後宮司家は代々「諏方祝子(すわほうり)」を称することとなります。また祝子の守役となった、初代祝子の母の家系は後の「六郷氏」へ続いたとされます。この大祝為仲の裔は10代続いたと伝わります。この間、建久3年(1192年)に社殿改築の記録が残されています。この改築の頃には六郷野中に遷っていたものと思われます。
諏訪宮の社殿は信濃國諏訪大社の方角を向いて建てられています。
諏訪宮の社殿は信濃國諏訪大社の方角を向いて建てられています。
諏訪氏・二階堂氏下向
大祝の裔に男子が絶えたため、諏訪家から諏訪宗治が下向して11代となります。至徳2年(1385年:至徳は北朝年号、南朝では元中2年)に二階堂氏と同時期に当地六郷に下りました。二階堂氏は守役であった家系を継ぎ、後に六郷氏を称します。この時諏訪宗治に従い諏訪一族である一瀬(いちのせ)氏が補佐役として一緒に下ります。
以後200年、10代の間「諏方祝子」として宮司でありながら武家として二階堂氏(六郷氏)と共に戦場にあったと記され、また共に町づくりを進めて諏訪宮は六郷總鎭守となります。宮司家と六郷家は同族となり共に「六郷亀甲」を家紋、社家紋として使うようになります。また時の流れの中で一瀬家も融合していきます。
六郷をはじめとする秋田県内の小正月行事「かまくら」の呼称の発祥はこの時代に求めることができます。少なくとも六郷で行われる古くからの「かまくら」(「竹うち」ではなく)の形態は、鎌倉幕府において二階堂氏が管掌した「左義長」と同じものです。
六郷をはじめとする秋田県内の小正月行事「かまくら」の呼称の発祥はこの時代に求めることができます。少なくとも六郷で行われる古くからの「かまくら」(「竹うち」ではなく)の形態は、鎌倉幕府において二階堂氏が管掌した「左義長」と同じものです。
本荘藩六郷家と諏訪宮
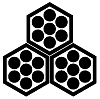
六郷氏が関ヶ原合戦に出陣の際(慶長5年8月15日六郷出立)、宮司(諏方祝子)は六郷城の執権を任せられて残ることになります。六郷政乗は徳川家に味方したため常陸國府中に1万石の領地を得て、再び六郷に戻ることはありませんでしたが、諏訪宮には代参が詣で、宮司も常州府中へ赴いています。この時六郷家からは「諏訪明神の隣国への国替え」の祈願を密かに命じられています。当時の常陸府中からの書状が現存します。この願いは元和4年(1618年)に実現し、六郷家は由利本荘に2万石を領して秋田に帰ることとなり、宮司は塩越まで出迎えています。
六郷家は尾崎城内に諏訪神社(現:本荘神社)を分社し、宮司が出向いて祭儀を執り行いました。また藩主の代替わり、宮司家の代替わり、跡取りの元服等に際しては必ず御城に登り挨拶するものとされ、また諏訪宮には毎年春に藩主の代参が詣でるのが恒例となりました。この代参は明治維新まで毎年行われ、その後も回数は減っても大東亜戦争終結まで続きました。代参の日までに参道の雪(氷)を全て取り除くことと、その日には他の祭儀を行わないとの慣例は戦後しばらくの間も続けられました。
久保田藩佐竹家と諏訪宮

慶長7年(1602年)秋田県の大半は佐竹氏の領地となり、六郷城には藩主佐竹義宣の父佐竹義重が入ります。この時を境に宮司家は神職専一となります。慶長9年(1604年)に佐竹義重により諏訪宮の本殿、拝殿、玉垣等が修造されました。この造営の棟札が現存しています。この時に社殿は現社地に遷されました。野中の次の鎮座地は六郷古町で、そこは現社地に遷座後も本宮(もとみや)と呼ばれ祝子一族 の社人が住みました。場所は現在「本宮山(ほんぐうざん)」の山号を持つ禅宗寺院の辺りです。この社人は本宮神主筑後守を称し、その所有地は「筑後屋敷」として現在も野中の字名に残っています。
この頃に、六郷に現在見られる多くの寺院が、周辺地域から集まって来ました。また熊谷氏・山口氏も修験として千屋から六郷に入り、熊野神社・神明社を創建し後に社家となります。修行院も同時期に六郷入りしますが、ここは明治維新まで修験でした。
慶長17年(1612年)佐竹義重が没し、六郷城は廃城となりました。城を六郷家から佐竹家へ引き渡す時、また廃城の際に城内の宝物や什物は宮司家に移されたとされますが、現代まで伝わっている物は「六郷公兜前立」ほか数点です。旧六郷城址本丸跡の土地は近年に至るまで宮司家の所有でした。
諏訪宮は藩南部の中心地、六郷の總鎭守という名社でありながら、藩内の有力神社とされた「藩内12社」にも入らず、競って拝領した「佐竹扇」紋とも無縁でした。これは本荘藩主六郷家との関係があまりにも密接であったため遠慮したものとされています。石高は10倍の違いがありますが、両藩の関係は友好的であったようです。後には久保田藩の役職にも就き藩主の宿ともなり、両藩から社領をいただくことになりました。
江戸時代の宮司家 齋藤則庸を中心に
12人の宮司が江戸時代を生きました。関ヶ原の合戦を機に神主専一になり、京都吉田家の裁許状を受けるようになります。京都を往復し中央の文化に触れ、学問にも向かうようになります。元禄の頃、諏方則重は「秋田の学問は友斎より始まる」と言われた梁田友斎から崎門学を学び、自身も県内に多数の門人を抱えました。他社家の記録に「六郷の齋藤日向守藤原則重の弟子」等の記載があります。男鹿と矢島に石碑がある、と伝わりますが未確認です。この則重の時に姓を「諏方」から「齋藤」に改めています 。
後三年の合戦後諏方祝子として宮司家が始まってから600年の間に諏方家、守役の家、二階堂家、六郷家、一瀬家が融合して一つの家になったものを、則重が元禄の頃に「齋藤」という姓を選んで名乗るようになるのです。この証跡は「紋」に見ることができます。現在宮司家で使用する紋は三つあります。「梶の葉」は神紋・社紋として宮司の装束に付けられます。紋付や羽織の正式の場合は「三盛り亀甲の内七曜(六郷亀甲)」を使い、私的な場合は「一の角字(一瀬家紋)」を用います。尤も今では曖昧になってしまっています。以前は祭典の時に神社の参道に「梶の葉」の燈籠、社務所の玄関に「六郷亀甲」、自宅としての社務所勝手口には「一の角字」の燈籠を掲げていました。大正の頃に使われた布袋には「諏訪神社社務所用」という文字と「一の角字」紋が染め抜かれていますので、線引きはなかなか難しかったようです。ちなみに、分家の齋藤家の家紋は「亀甲の内に一の角字」を使っています。

歴代の宮司の中で最も注目されるのが齋藤則庸(のりつね:安永7年1778~嘉永5年1852)です。幼少より学問を好み15歳で元服後、小瀬蔵人、中山菁莪に師事、28歳で伊勢松阪の本居大平へ入門します。家に残されていた旧記や古文書を全て整理再編また清書し直しました。役儀上の文書も悉く控えをとり、日々の日記を書き続けました。父則因の晩年の日記や、隠居後には息子則幸の日記の代筆をするという筆まめぶりです。諏訪宮や関連する神社の祭儀や年中行事は、この時に整理され定められたものが200年後の現在でも基本として受け継がれています。中には祭典後の直会の酒肴まで記録され、それが未だに守られているものがあります。則庸の執筆したものを『則庸日記』と総称しています。
齋藤家は国学を通じて社家大頭役で保呂羽山波宇志別神社の社家である大友家と交流があり、仙北六郷に住しながら雄勝平鹿両郡社人組頭となります。さらには大友、守屋の大頭二家に差障りのある場合には代理(名代)で保呂羽山や御嶽山の祭儀を行うこととなり、弘化2年には正式に大頭に次ぐ大頭格で寺社奉行直支配となります。
則庸は役儀の傍ら家塾(寺子屋)を開きます。筆子とよばれた塾生が通い、また遠くの子供は寄宿しました。「筆子50人を連れて東山に遊山」などと日記にみえます。則幸、則安と書き継がれ約千人の子供の名前を記した「同遊記」という家塾生名簿が残されています。後には塾生200人を超す「教育堂」となり、さらには明治9年開校の本道小学校へとつながっていきます。
諏訪宮と宮司家の特異性
現在秋田県内に鎮座する神社の多くは江戸時代を通じて、密教寺院か修験寺院かで、神社であってもそれらに支配された存在であり、仕える者もほとんどが僧侶か社僧か修験であり、また神職(社家)であってもそれらに従属する立場にありました。その中にあって諏訪宮・齋藤家は、密教寺院、修験寺院とはならず、また繋がりも持たず「神社」・「神主」の格式を保ち続けた稀な存在でした。
平成の今、県内神職家約280家の中で江戸時代から続いている家で、江戸時代にも「社家」とされているのは50家程です。密教寺院から神社・神職になった家は6家、修験寺院から神社・神職になった家は120家程です。他は明治以降に祀職となられた方々です。
この50家の中から明治維新前(江戸時代より前も含む)に密教寺院や修験寺院に社家として仕えた家や、神社であっても上に支配する別当寺院があったところ、「下社家」や明らかに他の神主に従属する家、「司官」「神楽役」とされた家を除くと、現在まで一貫して純粋な「神社」であり、その神前に「神主」として奉仕し続けているのは諏訪宮・齋藤家と他に数家だけのようです。
明治維新以後
明治の世となり神仏判然令が出されますが、仏教色のほとんど無かった諏訪宮には全く影響がありませんでした。明治元年に羽後國が設置されると、翌2年に「羽後國總鎭守諏訪宮」と称します。しかしやがて版籍奉還、廃藩置県により羽後國は無くなり神社名も「宮」は許されなくなり「諏訪神社」が正式名称となります。
明治14年(1881年)9月20日、明治天皇の東北御巡幸に際し宮司宅が御小休所となりました。御参拝はありませんでしたが、宮司をはじめ皆の喜びは想像を超えたものがあったと思います。『辛巳迎鑾記(しんしげいらんき)』等に詳細な記録が残ります。この時新築された御小休所の建物は老朽化しながらも現存しています。
宮司則安はこの光栄を無上のものとして、以後30年ひたすら神明奉仕にのみ日を送ります。御巡幸を機に社格の昇格を望むなどとは考えもしない人だったようです。周囲の人々は残念に思いながらも、その人柄を敬ったそうです。ただ後継者の問題では悲しみと懊悩の日々だったのです。神童と呼ばれた二人の子は幼くして亡くなり、迎えた養子も10代で病死。次に迎えた者は秋田魁新報の発刊に関わり罪を得て神職になれず(加藤則幹)、その長男は病弱で画家となり(橘小夢)、則幹の長女に迎えた婿は日露戦争で戦死、再び長女に婿を迎えてやっと跡継ぎに、という状況でした。
大正に入り則直の代になると神社の昇格が大きな話題となります。県内有数の、県南では第一の名社との自負心から、事情により留め置かれた村社から一気に県社への昇格を果たします。昇格に合わせて拝殿が建て替えられました。当時から県内第一の大きさと言われました。なお、現在の本殿は享保8年(1723年:徳川8代将軍吉宗の時代)の造営です。
この大正の昇格の際に尽力した氏子の中で、いずれ国幣社への昇格を目指すとの申し合わせがあったようですが、果たせぬまま昭和20年の終戦を迎えます。しかし、その意識は持続され神社本庁が設立されて間もなく、昭和28年には別表神社への加列が実現します。さらに昭和62年には正式な社名(法人登記)を「秋田諏訪宮」と改め現在に至ります。
御由緒 年表 も併せてお読みください。
